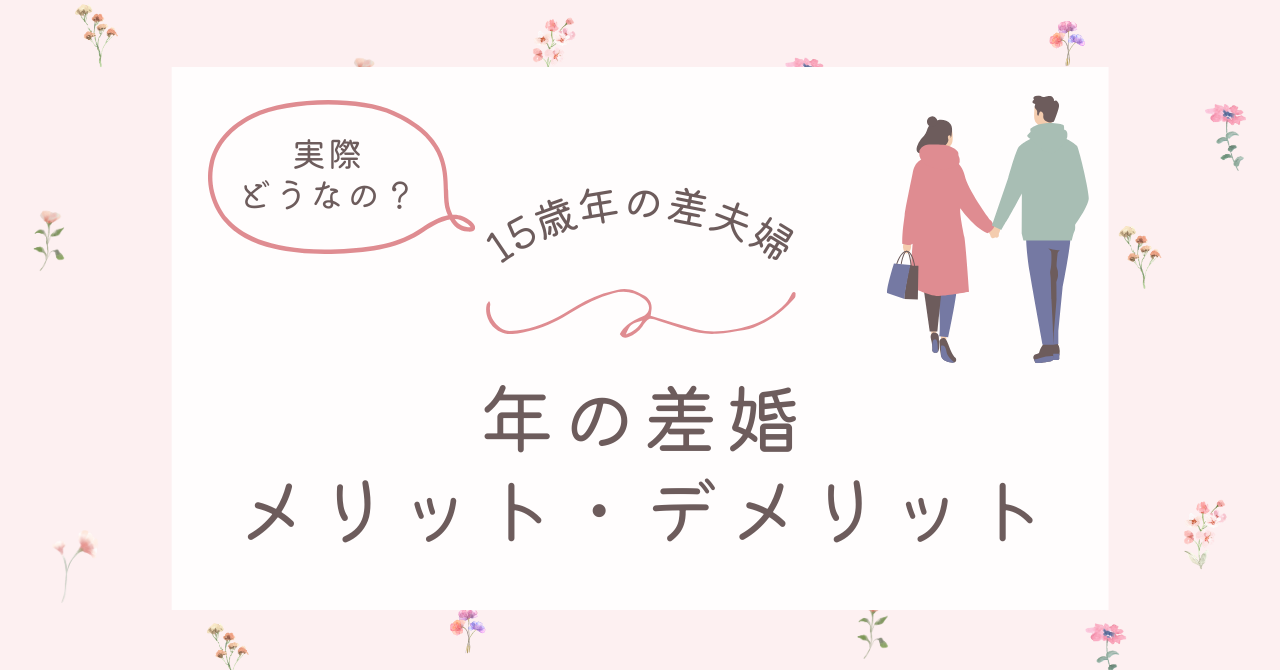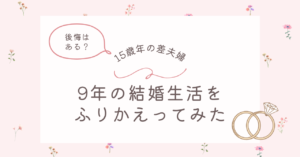お悩み女性
お悩み女性年の差婚って実際どうなの?
メリットやデメリットはある?
年上の彼がいる方や、10歳以上年上の男性が気になる方もいるのではないでしょうか。
将来を考えると「年の差婚は本当にうまくいくの?」と不安になりますよね。
私は、15歳年上の夫と結婚して9年になります。仕事を通じて知り合い、3年の交際期間を経て結婚しました。
この記事では、年の差婚をして感じた「よかったこと」と「後悔したこと」を、体験談を交えながらお伝えします。
はっきり言うと、年の差婚にはメリットもデメリットもあります。
大切なのは、理想だけでなく現実にも目を向け、自分が納得できる選択をすることです。
「年の差婚をしても大丈夫?」「好きだけど年の差が気になる」
そんな不安を抱える方に、少しでも気持ちをラクにするヒントや安心を届けられたら嬉しいです。
\大切な人と、自分らしく生きる/
はじめまして!ちょびです。
15歳差婚を経験している私が、「なんとなく不安…」から「いつでも幸せになる」ために役立つ情報をお伝えしています。
プロフィールはこちら
年の差婚はそれほど珍しくない


2021年の厚生労働省「人口動態統計」によると、初婚夫妻の年齢差別にみた構成割合では、男性が年上のケースは56.3%と報告されています。
つまり、2人に1人以上が年上の男性と結婚しているという結果です。
さらに、7歳以上年上の男性と結婚している割合は10.5%にのぼります。
実は今から30年前の平成7年(1995年)も10.9%と、年の差婚の割合はほぼ変わっていません。
年の差婚は「珍しい」と思われがちですが、実際にはそれほど珍しいことではないと分かります。
マッチングアプリやSNSの普及、芸能人の年の差婚のニュースなどの影響で、年齢にとらわれない出会いが増えているともいえるでしょう。
年の差婚のメリットは「安心感」


年の差婚は、周囲から驚かれることが多く、将来への不安を心配されるケースもあります。
ですが、落ち着いた雰囲気を持つ年上男性には、同年代にはない「安心感」があると感じる人もいます。
ここでは、年の差婚のメリットを3つご紹介します。
経済面・精神面での安定
年上のパートナーは、社会人としてのキャリアが長いため、役職に就いていたり、収入が安定していたりすることが多いです。
働いてきた期間も長いぶん、貯蓄や投資に取り組んできた年数も多く、ある程度の資産を築いている場合もあります。
また、人生経験が豊富なため、トラブルが起きても冷静に判断でき、精神的にも落ち着いた対応をしてくれる存在です。
経済的・精神的な安心感は、結婚相手として非常に大きな魅力の一つです。
人生経験の差から生まれる学びや刺激


年上の方は、これまでにさまざまな経験を積み重ね、豊かな人生を歩んできました。
失敗や挫折を乗り越える中で、冷静に物事を判断し、問題を解決する力を身につけてきた人も多いでしょう。
年上パートナーの経験談からは、感情に流されない落ち着いたアドバイスを受けることができます。
自分だけでは思いつかない視点に触れ、知らなかった世界や考え方を学べる貴重な機会になります。
人生経験の差から生まれる学びや刺激は、新たな価値観を発見し、より豊かな人生へと導いてくれるものです。
お互いを尊重しやすい関係性
年の差があるからこそ、自分が知らない世界や考え方に触れる機会が増えます。
価値観や視点の違いによって、「そんな考え方もあるのか」と相手を理解しようとする気持ちが自然と生まれるのです。
年齢が離れているぶん、育ってきた時代や人生観にも違いがあるでしょう。
その違いをきっかけに、相手の意見に耳を傾け、自分の考えを見直すことができます。
相手の意見を認めることで、自分の意見も尊重され、対等で思いやりのある関係が築きやすくなるものです。
年の差婚のデメリットは「年齢」
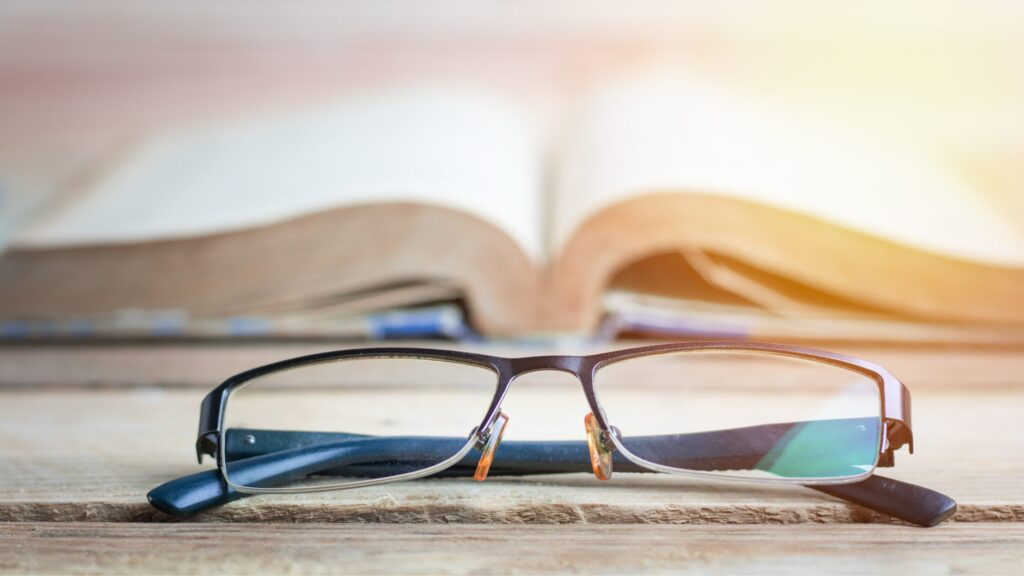
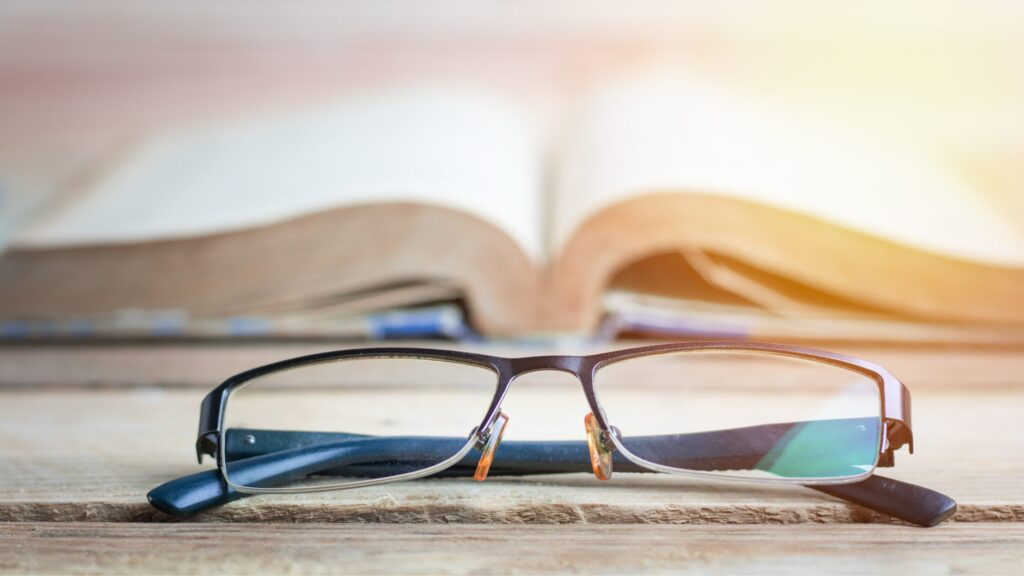
年の差婚が珍しくないとはいえ、年齢差が大きいことで生じる現実的な課題もあります。
ここでは、年の差婚のデメリットを3つご紹介します。
育児や介護の問題
年齢差が大きくほど、育児や介護の問題に直面する可能性が高まります。
出産や子育てのタイミングで「夫の体力に自信がない」「健康面が不安」と感じる場面も出てくるでしょう。
パートナーの親の年齢が高いため、義両親の介護と育児が重なる「ダブルケア」になる可能性もあります。
その場合、自分自身の体力や健康面にも影響が出てくることがあります。
育児や介護については、事前にどのような役割分担が良いか、サポートをどう確保するかを考えておく必要があります。
価値観やライフスタイルの違い


育ってきた時代や環境が異なれば、価値観やライフスタイルも自然と違ってきます。
年上パートナーは独身生活が長いぶん、生活習慣や考え方に違和感を覚えることがあるでしょう。
日々の会話でも、流行の音楽やエンタメの好みが合わなかったり、思い出話に共感できなかったりすることがあります。
特に、家事やお金の使い方、休日の過ごし方、家族との関わり方など、毎日の生活に直結する部分で違和感を抱いた場合は、放置せず早めに話し合うことが大切です。
お互いを尊重し、価値観の違いを楽しめる関係であれば問題はありません。
ですが、小さなすれ違いが積み重なり、大きなストレスにつながることもあります。
価値観の違いを乗り越えるには、
- 自分の意思を具体的に伝える
- 考え方の違いを否定せず、相手の意見に耳を傾ける
- 「価値観は違って当たり前」と受け止める
少しの考え方や接し方の工夫で、価値観の違いを受け入れ、良好な関係を築くきっかけに変えられます。
老後や将来への不安


厚生労働省の発表によると、令和5年度(2023年)の日本人の平均寿命は男性81歳、女性87歳で、男女の差は6年あります。
男性が年上の場合、年の差に加えて6歳(平均寿命)の差があるため、女性がひとりで過ごす期間は長くなる可能性が高いです。
年の離れた夫がいる場合、夫に先立たれる可能性は高く、その分ひとり残された期間が長くなります。
また、夫が老後を迎えても、妻はまだ働き盛りのケースもあります。妻が定年退職を迎える頃には、すでに夫が亡くなっており未亡人になる可能性もあるでしょう。
年の差婚では、同年代の夫婦と比べて、2人で老後を楽しめる期間が短くなりやすいという現実があります。
老後の過ごし方や、2人で過ごす時間について、早めに話し合い、計画を立てておくことが大切です。
お金にまつわるメリット・デメリット


年の差婚では、将来への不安を感じる場面が少なくありません。
ここからは、生活の中でも特に重要な「お金」に関するメリット・デメリットをご紹介します。
お金の話はパートナーに相談しづらいですが、2人で暮らしていくためには避けて通れないテーマです。
年の差婚だからこそ生まれる、お金のメリット・デメリットをまとめました。
メリット① 年上パートナーの収入や資産による生活の安定
年上パートナーは、社会人としての経験が長く、勤続年数や役職によって高収入を得ている可能性があります。
また、若い頃から積み重ねてきた貯蓄や投資によって、資産を築いているケースもあるでしょう。
経済的な土台があることで、生活にゆとりが生まれ、旅行や趣味なども楽しみやすくなります。
人生の3大支出とされる「教育・住宅・老後」の資金も、計画的に準備できるため大きな安心感につながります。
経済面での安定は、精神面の安心にもつながり、結婚生活を長く支える大きな要素となるのです。
メリット② 年の差があるほど年金が増える「加給年金」
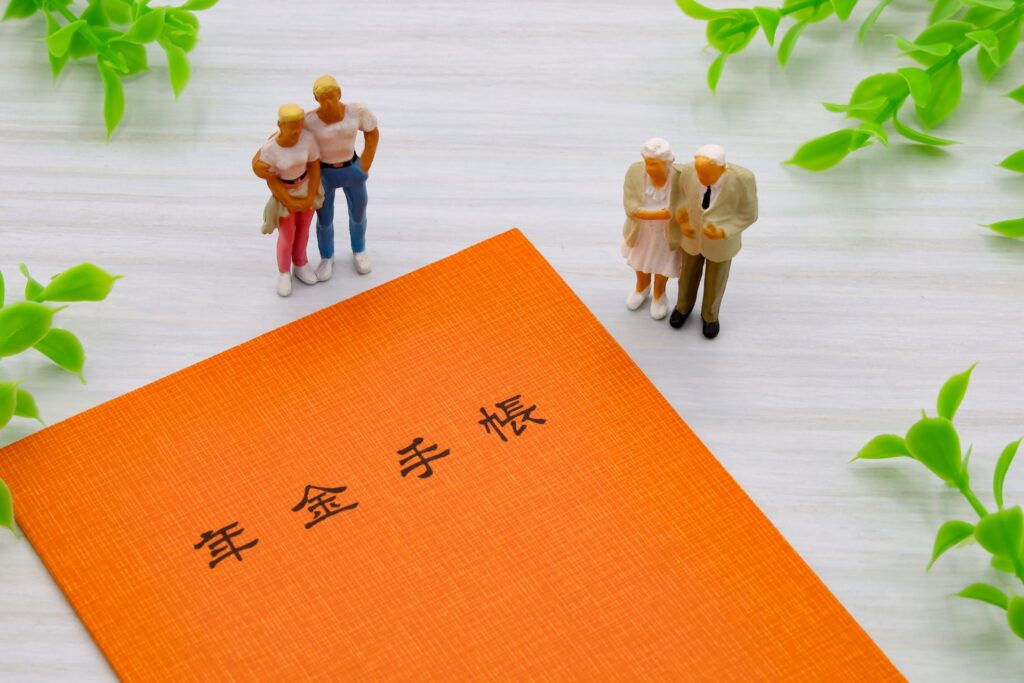
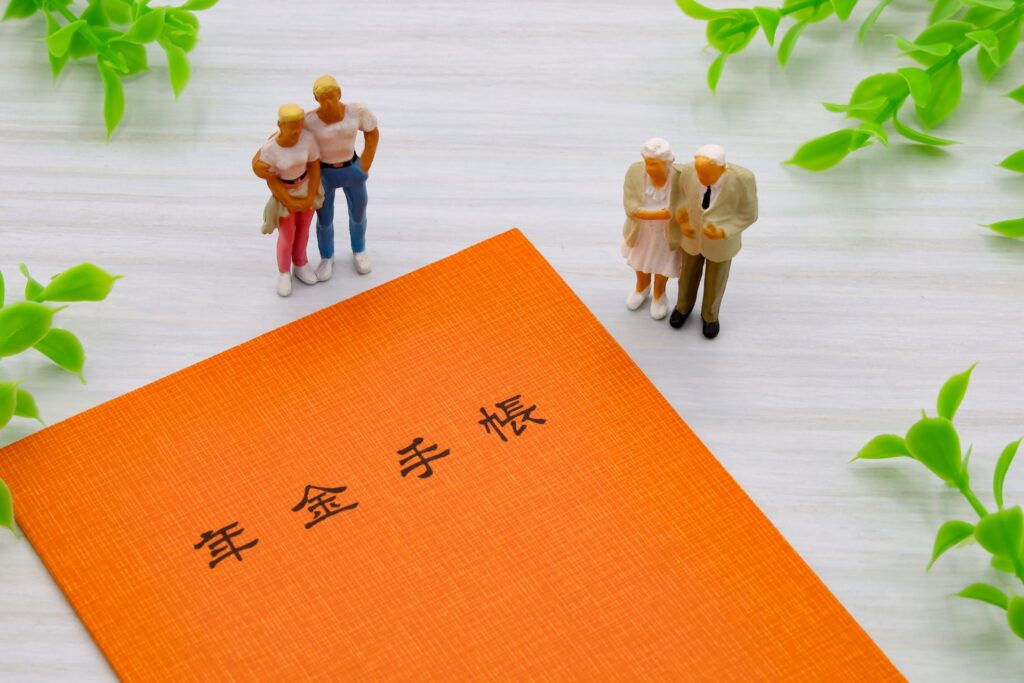
年金制度には、厚生年金の被保険者が65歳になったとき、扶養する配偶者や子どもがいる場合に支給される「加給年金」というものがあります。加給年金は「年金における家族手当」と呼ばれ、老齢厚生年金にプラスして支給されます。
例えば、夫が厚生年金に20年以上加入しており、65歳未満の妻がいる場合、妻自身の年金受給年齢(65歳)までの10年間、加給年金が支給されます。年の差があるほど、加給年金の支給年数が長く、受け取れる年金の総額が多くなるのが特徴です。
2025年6月に年金制度改正法が成立し、加給年金の年額は408,100円(2024年価格の年額)から367,200円に減額されることが決まりました。(2028年4月施行)
夫婦の年齢差ごとにもらえる加給年金の総額は以下のとおりです。
| 年齢差 (夫 > 妻) | 支給年数 | 総額(2024年価格) | 総額(2028年4月以降) |
|---|---|---|---|
| 5歳差 | 5年 | 2,040,500円 | 1,836,000円 |
| 7歳差 | 7年 | 2,856,700円 | 2,570,400円 |
| 10歳差 | 10年 | 4,081,000円 | 3,672,000円 |
| 12歳差 | 12年 | 4,897,200円 | 4,406,400円 |
| 15歳差 | 15年 | 6,121,500円 | 5,508,000円 |
10歳差の場合、約400万円(減額後約367万円)が夫の老齢厚生年金にプラスして支給されます。
ただし、配偶者が厚生年金に20年加入している場合は、支給対象外となるため注意が必要です。
また、年金制度の改正により、加給年金は縮小傾向にあります。今後も改正される可能性があるため、最新情報を確認しておくことが大切です。
とはいえ、夫が年金受給のタイミングで生活費の負担を軽減してくれる「加給年金」は、年の差夫婦にとって大きな助けになります。
デメリット① 子どもの進学と定年退職による収入減少


年の差婚では、パートナーの定年退職による収入減少と、子どもの教育費が最もかかる時期が重なる可能性があります。
例えば、40歳で子どもが生まれ場合、子どもが20歳になる頃には、パートナーは60歳の定年を迎えます。
もし子どもが大学に在学中であれば、残り2年分の学費が必要です。文部科学省の調査によると、令和5年度の私立大学に係る年間授業料の平均は文系が827,135円、理系では1,162,738円です。
遠方の大学に進学した場合は、学費だけでなく生活費や仕送りも必要になるでしょう。日本学生支援機構(JASSO)の令和4年度学生生活調査結果では、食費、住居・光熱費などの生活費の平均は年間677,400円とされています。
教育費のピークと収入減少が同時に訪れると、家計への負担は非常に大きくなります。そのため、早い段階から資金計画を立てておくことが重要です。
デメリット② 価値観の違いによる金銭感覚のズレ


価値観の違いから、お金の使い方にズレが生じることがあります。
独身生活が長ければ、家計を気にせずお金を使う人も少なくありません。
しかし、夫婦ともに独身時代の感覚でお金を使っていては危険です。
結婚後は、教育費や住宅購入、老後資金など、家族に関わる大きな出費が必要になるからです。
お金に対する考え方が異なると、家計のやりくりだけでなく、日常生活にも不安を感じやすくなります。
節約思考の妻と浪費傾向のある夫では、理解し合えず衝突するケースもあるでしょう。
趣味や好みが違っても大きな問題にはなりませんが、お金に関する価値観の違いは妥協しにくいものです。
「何にお金を使うのか」「そのお金からどんな価値を得たいのか」を2人で共有しておくことが大切です。
家計管理・老後資金のすり合わせ方法


お金の価値観をすり合わせるには、夫婦で話し合うことが大切です。
とはいえ、夫婦であってもお金の話は切り出しにくいテーマです。
教育費や老後資金を準備するためには、ライフプランを立て、計画的に家計管理していくことをおすすめします。
ライフプランとは、「いつ、何に、いくら必要か」を見える化する人生の計画書です。
家計管理の基本は、収入と支出を把握し、家計簿をつけ、収入の範囲内で生活すること。
夫婦のどちらか一方に任せるのではなく、共有しながら一緒に進めることが重要になります。
夫婦で話し合うと良いテーマは、以下の5つです。
- 子どもの教育費(学費、習い事など)
- 住宅にかかる資金(住宅ローン、リフォーム費用など)
- 老後の備え(生活費、医療費、介護費用など)
- 毎月の生活費(食費、光熱費など)
- 趣味や旅行(人生を楽しむためのお金)
お金の話し合いは気まずさもありますが、「何にいくら必要か」を整理することで、支出の優先順位をつけることができます。
ライフプランを立てることは、限られた時間をどう過ごすかを考えるきっかけにもなります。
小さな習慣から始めれば、安心して未来を築ける資金を準備できるでしょう。
【体験談】年の差婚で「よかった」と感じた瞬間


15歳年上のパートナーと結婚して9年。交際期間を含めると、10年以上を共に過ごしてきました。
結婚後は3人の子どもに恵まれ、義母との同居がスタートしました。
ここからは、年の差婚で「よかった」と感じた体験談をお話しします。
ケンカがない穏やかな関係
私たち夫婦はどちらも争いを避ける性格で、交際当初からケンカはほとんどありません。
子どもについては時間を取って話し合いますが、日常生活や趣味に関しては干渉せず、それぞれを尊重しています。
とはいえ、心に余裕がなくなると険悪な雰囲気になることもあります。
疲れて相手に優しくできないときは、あえて距離をとることを心がけています。
イライラしても、1人で気持ちを整理すれば、時間とともに自然と落ち着けるからです。
その一方で、相手を思いやり、感謝の気持ちを言葉にすることも欠かせません。
例えば、料理や洗濯をしてくれたときは「ありがとう」、子どもの送り迎えをしてくれたときは「助かります」と一言添えるようにしています。
小さな思いやりや言葉が夫婦関係を和らげ、穏やかな関係を支えてくれるのだと感じています。
年齢差による学びや発見


年齢や生きてきた時代が違うことで、日常の小さな出来事や仕事、人間関係に対する考え方にも違いがあります。
過去の経験や考え方の違いから、新しい視点や学びを得られるのが年の差婚の魅力です。
結婚当初、家事の進め方で意見が食い違ったことがありました。
私は「できる方が家事をやれば良い」という考えでしたが、夫は「自分のことは自分でやるべきだ」という考えを持っていました。
話し合ううちに、「自分でできることは自分でやろう」と私の意識が変わりました。
一方の夫は、「協力して家事を行うことも大切」だと気づいたそうです。
お互いの違いを認め合い、意見を交換することで、新しい学びや発見に繋がり、夫婦関係がより成長していくと実感しています。
【体験談】年の差婚で「後悔した」と感じた瞬間


15歳年上の夫と結婚してよかったことは多くありますが、「やっぱり年の差があるから…」と後悔する瞬間もあります。
ここでは、私が年の差婚で「後悔した」と感じた体験談をお話しします。
加齢により体力や気力が落ちる
出会ったころは30代の夫も、いまは40代後半のアラフィフです。
私自身も感じますが、やはり年齢による体力と気力の衰えは避けて通れません。
結婚前と比べると、夫の体力と気力の衰えはより大きく感じます。
休日に家族みんなで出かけたいと思っても、なかなか行動できず、結局ダラダラと1日中家で過ごしてしまうことも多くあります。
子どもを見ていてほしいとお願いしたのに、気づけば夫だけ寝ていることも。
「仕事で疲れているから仕方ない」と理解しつつも、「せっかくの休みだから一緒に楽しみたかった」と少し残念に感じてしまいます。
40代後半に入ってからは、体調を崩す回数も増えてきたように感じます。
加齢による体力や気力の衰えは、誰にでも訪れるものです。
だからこそ、「今できることを大切にしよう」と気持ちを切り替えるようにしています。
子どもを望めるタイムリミットがある


年の差があると、子どもを望める期間が短くなるという現実があります。
その理由は、主に以下の3つです。
- 体力の衰えによる子育てへの不安
- 教育費のかかる時期と収入減少が重なる経済的不安
- 加齢による不妊リスク
体力や経済的な理由で、「子どもは何人望むか」「何歳までに産んだ方がよいか」というリミットがあるのは事実です。
私の場合、15歳年の差があるので、夫の年齢と経済的な理由から4人目の子どもは諦めました。
仮に4人目を授かれたとしても、私が35歳のとき夫は50歳。
子どもが10歳になるころには、夫は60歳で定年を迎えます。
これから教育費がかかるというタイミングで退職による収入減少を考えると、現実的に難しいと感じました。
年金暮らしになってからも養わなければならない子どもがいるのは、大きな負担です。
そのためにも、夫婦でよく話し合い、無理のない家族計画を立てることが大切だと実感しています。
まとめ:メリットとデメリットを知って、納得できる決断をしよう


年の差婚には、メリットもあればデメリットもあります。
年齢差そのものは変えられませんが、考え方や将来への準備次第で不安を減らすことはできます。
大切なのは、理想だけでなく現実にも目を向けて、納得できる選択をすることです。
1人で抱え込まず、パートナーや信頼できる人に相談すると、新たな価値観に出会え、安心して進んでいけるはずです。
後悔のない、自分らしい人生を築いていけますように。
信頼できるパートナーと、今日からライフプランについて話し合う一歩を踏み出してみませんか。
これからも「大切な人と、自分らしく生きる」ために情報発信していきますので、「年の差婚ナビ」を楽しんでいただけたらうれしいです!
最後まで読んでいただきありがとうございました!