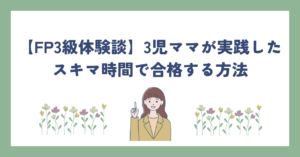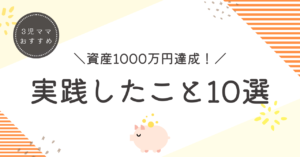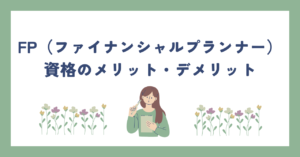「夜の寝かしつけに時間がかかり困っている」
「なかなか寝ない子どもにイライラしてしまう」
そんな毎晩に疲れていませんか。
怒るつもりはなかったのに、思わず「早く寝てよ!」と、つい強い口調になってしまうこともありますよね。
子どもの寝顔を見ながら「本当は怒りたくなかったのに」と後悔する日々。私自身、同じ経験を何度も繰り返してきました。
私は、15歳年上の夫と結婚し、3人の子どもを育てるワーママです。第一子が生まれてから今日まで、毎晩寝かしつけをしてきました。
その中で感じた後悔や自己嫌悪、そして試行錯誤の末にたどり着いた「最高の寝かしつけ」方法があります。
結論はとてもシンプルで、「子どもと一緒に寝ること」。
この記事では、3人の寝かしつけを経て効果のあった実践法をご紹介します。
「子どもの寝かしつけに悩んでいる」「寝ない子どもについイライラしてしまう」
そんなあなたの心が少しでも軽く、ラクになれば嬉しいです。
\大切な人と、自分らしく生きる/
はじめまして!ちょびです。
15歳差婚を経験している私が、「なんとなく不安…」から「いつでも幸せになる」ために役立つ情報をお伝えしています。
プロフィールはこちら
最高の寝かしつけは、子どもと一緒に寝ること

寝ない子どもの寝かしつけは、想像以上に心身を消耗します。
私自身も何年も試行錯誤しましたが、最終的に一番効果があったのは「子どもと一緒に寝ること」でした。
ここでは、なぜ一緒に寝ることが寝かしつけに最適なのかを解説します。
「寝かしつけ」と「一緒に寝る」の違い

「寝かしつける」とは、親が子どもを寝かせようとする行為です。
一方で「一緒に寝る」とは、親子が同じ布団でリラックスしながら自然と眠りに入ることです。
「子どもが寝る」という行動は同じですが、親の心の持ち方に大きな違いがあります。
多くの親にとって、寝かしつけの後には「家事を終わらせたい」「自分の時間をつくりたい」という思いがあるでしょう。
その思いは、子どもがなかなか寝ないことで「やりたいことができない」という強いストレスに変わります。
「一緒に寝る」と決めると、親の心に余裕ができます。
「子どもを寝かせる」のではなく「自分も休む時間」と考えられるからです。
親がリラックスして横になっていると、不思議と子どもも安心して眠りにつきやすくなります。
一緒に寝ることは、子どもにとっても親にとってもストレスの少ない寝かしつけなのです。
一緒に寝ることのメリット

子どもと一緒に寝る最大のメリットは、親自身の睡眠時間を確保できることです。
特に乳幼児期は授乳や夜泣きへの対応に追われ、睡眠時間が短くなりやすいです。睡眠不足はイライラやストレス、体調不良の大きな原因にもなります。
「子どもを寝かせたら家事をしよう」と考えると、寝かしつけが長引くほど焦りや苛立ちが募るもの。
発想を切り替え、子どもが寝る前に家事を済ませ、一緒に休むことで気持ちがぐっとラクになります。
ただし、ワンオペ育児ではやることが多すぎて、すべてを1人で完璧にこなすことは不可能です。
時短家電を取り入れたり、夫婦の家事分担を見直したりして、負担を減らすことが大切です。
「親子でリラックスできる環境」を整えることが、寝かしつけの成功につながります。
子どもが寝ない原因(年齢順)
子どもが寝ない原因には、さまざまな要因があります。
年齢ごとに特徴的な原因を理解しておくと、より適切な対処法を考えられるようになります。
ここからは、年齢ごとに寝ない原因を解説していきます。
0歳:生活リズムが安定しない

生まれたばかりの赤ちゃんは、昼と夜の区別がついていません。
生後3ヶ月頃から徐々に体内時計が整ってくるといわれています。
この時期の赤ちゃんが眠れない理由は、オムツが気持ち悪い、お腹が空いている、暑さや寒さなどさまざまです。
赤ちゃんの様子をみて、原因をひとつずつ解消してあげることが大切です。
毎日同じ時間に寝かせるのは難しいですが、20時には部屋を暗くして布団に寝かせるといったルーティンを続けると生活リズムが整いやすくなります。
ただし、成長には個人差があります。焦らず、赤ちゃんのペースに寄り添うことが安心につながります。
1歳:遊びたい気持ちが強い

1歳になると歩いたり言葉を発したりと、できることが一気に増えます。
体力もついてくるため、遊びたい気持ちが強くなり、夜なかなか寝ない原因になります。
お昼寝の時間が遅いと、夜に目が冴えてしまうこともあるでしょう。
日中しっかり体を動かすことで、夜の自然な眠気につながります。
1歳になると夜まとまって眠るようになり、親もようやく自分の睡眠を確保できるようになります。
ただし成長には個人差があるため、夜泣きが続く子もいます。夜泣きは、睡眠サイクルの未発達や、日中のちょっとした刺激・興奮が原因となることが多いです。
その時は、生活リズムやリラックスできる寝室環境を整えるなど工夫して対処していきましょう。
2~3歳:自我の発達とイヤイヤ期

2〜3歳頃になると自我が芽生え、自分の意思や要望をはっきり言葉や行動で伝えるようになります。
「まだ寝たくない!」という感情が強く、なかなか寝つかないことも多くあります。
気持を言葉で伝えられるようになりコミュニケーションは取りやすくなりますが、一方で何を言っても「イヤ!」と反発される場面も増えるでしょう。
親の言葉を理解できるようになっているため、「もう寝る時間だよ」と毎日同じ言葉で伝えることが効果的です。
声掛けを繰り返すことで、子どもにとって「寝る時間=眠る準備をする時間」と認識しやすくなります。
さらに、日中にたくさん身体を動かし生活リズムを整えることで、夜の入眠がスムーズになります。
4歳以上:昼寝や生活習慣の影響

4歳を過ぎると、保育園や幼稚園などの集団生活が始まる子が多くなります。
日中の活動量が増えることで体力がつき、昼寝をしなくなる時期です。
昼寝をやめたことで早く眠くなり、夜ぐっすり眠れる子もいます。
一方で、園から帰宅した夕方に眠気が訪れ「夕寝」をすると、夜に目が冴えてしまいなかなか寝つけないことも。
園生活が始まると、親も子どもも生活リズムが大きく変わります。
「眠そうだから、ご飯の前にお風呂に入ろう」「疲れている様子だから30分だけ寝かせてあげよう」など、子どもの様子をみながら柔軟に対応することが大切です。
ちょっとした工夫で夜の寝かしつけがスムーズになり、親子ともに落ち着いて過ごせるようになります。
寝ない子どもにイライラする原因

寝かしつけは毎晩必ずやってきます。
そのため、毎日何時間もかかるとイライラが溜まってしまいますよね。
怒ることではないと分かっていても、つい「早く寝てよ!」と子どもを責めてしまうこともあります。
ここからは、寝ない子どもにイライラしてしまう原因を3つ解説します。
イライラの原因を理解することで、感情をコントロールしやすくなり、寝かしつけを少しラクにできるはずです。
「〇〇時までに寝かせなければ」というプレッシャー

厚生労働省のガイドラインでは、米国睡眠医学会の推奨を参考に、以下のような睡眠時間が目安とされています。
- 1〜2歳児:11〜14時間
- 3〜5歳児:10〜13時間
- 小学生:9〜12時間
- 中学・高校生:8〜10時間
心身の健康を保つために、睡眠時間は子どもの成長にとても重要です。
そのため「子どもの健康のために、〇〇時までに寝かせないと」と考えてしまい、プレッシャーにつながることがあります。
「もうこんな時間!」「早く寝かせなきゃ」という焦りが、イライラを大きくしてしまうのです。
しかし、実際の寝かしつけは毎晩思い通りにはいきません。
夜寝るのが遅くなった日は、翌日の昼寝で調整するなどして睡眠時間を確保してあげましょう。
睡眠時間が短くても元気な子もいるため、心配しすぎないことも大切です。
推奨時間はあくまで目安。子どもの様子を見ながら柔軟に対応することで、親の気持ちもラクになります。
子育てと睡眠不足による心身の疲れ

新生児〜乳幼児期は毎日バタバタして、気がつけばあっという間に1日が終わってしまいます。
親自身がどれほど疲れていても、子どものお世話が優先となり、睡眠時間は短くなりやすいです。
子育て中は思うように休めない状況が続き、心身ともに疲れが溜まっていくばかり。
体の疲労だけでなく気持ちの余裕も失われ、些細なことでイライラすることが増えてしまいます。
子育てに疲れたと感じたときは「自分ひとりで頑張らなければ」と抱え込まず、誰かに助けを求めましょう。
パートナーや両親、友人、行政の支援やベビーシッターなど、誰かに頼ることも大切です。
親が心身ともに健康でいることは、子どもに優しく向き合うための土台です。
心に余裕が生まれることで、寝かしつけのイライラも軽くすることができるでしょう。
自分の時間が奪われるストレス

子どもの寝かしつけに1〜2時間もかかると、「自分の時間がなくなる」と感じてストレスになることがあります。
「子どもが寝たら家事をしよう」「夜にひとり時間を楽しみたい」と考えている親にとって、子どもがなかなか寝てくれないのは大きな負担です。
頭では「仕方ない」と分かっていても「早く寝てよ!」と、ついイライラしてしまうもの。
そんなときに限って、子どもは余計に目を覚ましてしまいます。
焦りや苛立ちは子どもに伝わるので、寝かしつけがさらに長引く悪循環に陥ります。
そんなときは「早く寝てくれたらラッキー」と考えてみると良いでしょう。
完璧に「自分の時間をつくる」のではなく、子どもが寝たタイミングでできることをやる。そう割り切るだけで気持ちが少し軽くなるものです。
一緒に寝るためのタイムスケジュール

子どもを早く寝かせるためには、親もリラックスして一緒に休むことが大切です。
とはいえ、子育て中は家事をこなすだけでも精一杯。
特に仕事をしている場合は時間も限られ、「子どもと一緒に寝たら家事ができない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
ここからは、私が実践している「子どもと一緒に寝るための工夫」をご紹介します。
夕方からの過ごし方で決まる
子どもと一緒に寝るためには、夕方からの過ごし方がカギになります。
ポイントは、帰宅後の行動をルーティン化すること。
毎日同じ流れを繰り返すことで、子どもの生活リズムが整い、自然と寝る時間も決まっていきます。
夕方に効率よく家事を進めるコツは、以下の2つです。
- 朝の時間を活用して準備する
- 手抜きしながらこなす
朝ご飯を作りながら夕飯の下ごしらえをする、夕飯のメニューを固定化して迷わないようにするなど、料理の負担をなるべく減らすようにしています。
帰宅後にすべて一から準備すると時間がかかり大変です。だからこそ「できるときにやる」「疲れている日は手抜きする」という切り替えが大切なのです。
「完璧に家事をこなす」よりも「無理せず続けられること」を最優先に。
家事を多少手抜きしても問題ありません。無理をしない工夫が、親子で穏やかに眠ることができる第一歩です。
帰宅後のタイムスケジュール
平日夕方のスケジュールは以下のとおりです。
通勤に加えて保育園と学童への迎えがあるため、夕方にはすでにクタクタ。
帰宅後はソファに倒れ込みたい気持ちをこらえ、夜に子どもたちと一緒に寝るために、ここで気合を入れ直します。
16:00 退勤
17:30 学童お迎え
17:45 保育園お迎え
18:00 帰宅
18:10 夕飯準備
18:40 お風呂
19:15 夜ご飯
20:00 歯磨き&翌日の準備、洗濯開始、子ども達と自由時間
20:50 洗濯物を干す
21:00 就寝
我が家は「お風呂→ご飯→歯磨き&翌日の準備→自由時間→寝る」の流れを、赤ちゃんの頃からずっと変えずに続けています。
子どもが小さい頃は「20:00就寝」を目標にしていましたが、私が仕事を始めてからは「21:00就寝」が現実的なラインになりました。
ですが、3歳と5歳の子どもにとっては20:00就寝が理想です。
眠たそうな様子が見られるときは、臨機応変に先に寝かせることもあります。
大切なのは、時間を守ることではなく、子どもの様子に合わせて柔軟に対応することだと実感しています。
就寝時間にこだわりすぎないことで親のイライラも減り、子どもも安心して眠りやすくなります。
寝るまでの流れをルーティン化

夜の寝かしつけをスムーズにするには、毎晩のルーティンにかかっています。
「そろそろ寝る時間だな」と子どもが自然に感じられるよう、毎日の習慣づくりが大切です。
寝る前のルーティンのポイントは以下の4つです。
- 夕飯の前にお風呂に入る
- 歯磨き&翌日の準備をセットで行う
- 21:00になったら寝室へ行く
- 寝室は照明を暗くする
我が家では、夕飯の前にお風呂に入るようにしています。
疲れている日は、食べながらウトウトしてしまうことも。先にお風呂を済ませておけば、眠たいときは寝かせてあげられるので安心です。
また、夕飯後は「歯磨きと翌日の準備」をセットで行い、「終わったらあとは寝るだけ」という流れをつくっています。子どもたちも「支度ができたら少し遊べる」と理解しているので、スムーズに進めやすくなりました。
日によっては夕飯が 20:00になることもありますが、21:00には必ず寝室へ。
寝室は照明を暗くし、眠れないときは会話やしりとりをして過ごします。
気がつけば私が先に寝てしまうこともありますが、暗い環境にいると子どもも自然と入眠モードに入ります。
最後に「おやすみ」と声をかけて寝るのも大切な習慣です。
最初はゴロゴロしてなかなか寝なくても、同じ流れを繰り返すことで少しずつ寝やすくなっていきます。
親子でリラックスして一緒に眠れるよう、無理のない範囲でルーティン化してみるのがおすすめです。
夫婦で協力して家事を行う

子どもと一緒に夜早く休むためには、家族の協力が欠かせません。
我が家の基本的な分担は、私が料理、夫が洗濯です。掃除は休日や余裕のあるときに行っています。
私が土日休みで夫がシフト制のため、休日が合わないことも多いです。その場合は、夫が平日休みの日に子どもの迎えや夕飯を担当。逆に夫が忙しい日は、私が夕飯後に洗濯を済ませてから就寝します。
大切なのは「分担を固定する」よりも「できる人ができるときにやる」という柔軟さ。
役割をきっちり分けてしまうと、予定通りにいかないときにストレスになります。
お互いに助け合いながら家事を回すことで、無理なく子どもと一緒に眠る時間を確保できます。
「家事を完璧にこなすこと」よりも「家族みんなが笑顔で過ごせること」をゴールにすると、寝かしつけも自然と続けられるものです。
【体験談】寝かしつけの失敗

寝かしつけを始めて7年。3人の子ども達と過ごす中で、「あれは失敗だったな」と後悔することが何度もありました。
ここからは、私が実際に経験した寝かしつけの失敗を3つご紹介します。
寝室におもちゃを置いていた
我が家は寝室の隣にリビングがあります。
気がつくと、おもちゃや絵本が寝室に紛れ込んでいることがよくありました。
お昼寝前に布団の上で遊んだり、絵本を読んだりして、そのままになっていたのです。
部屋の隅に置いても子どもにとっては気になる存在で、眠気よりも遊びたい気持ちが勝ってしまいます。
それからは「寝室にはおもちゃや絵本は持ち込まない」とルールを決め、遊んだら必ずリビングへ片付けるようにしました。
寝る前に激しく遊ばせすぎた
夕飯後は20時頃から子どもの自由時間になります。
眠たければそのまま寝ますが、元気な日は21時頃まで遊んでいます。
静かにブロックや絵本を楽しむ日もあれば、戦いごっこで大騒ぎになる日も。
激しい戦いの後は興奮して寝つけず、寝かしつけに苦戦しました。
今は、レゴやLaQ、トランプなど座って楽しめる遊びを取り入れています。
寝る前は「刺激を減らす」ことが、スムーズな入眠につながると実感しています。
寝る直前に帰宅したパパと遭遇
お風呂・夕飯・歯磨き・支度を終え、あとは寝るだけというタイミングでパパが帰宅。
その瞬間、子どもたちは嬉しさから大興奮です。
直接会わなくても、車の音やドアの音で「パパ帰ってきた!」と敏感に反応することもあります。
夫の帰宅が子どもの就寝時間と重なりそうなときは事前に連絡し、近くのコンビニで待機して帰宅時間をずらしてもらうこともありました。
今ではパパが帰ってきても「おかえり!」と喜びますが、就寝時間と分かっているため「おやすみなさい」と言って、寝室へ行くようになりました。
改めて毎日の習慣は大事だと感じています。
【体験談】寝ない1歳児に悩んだ日々
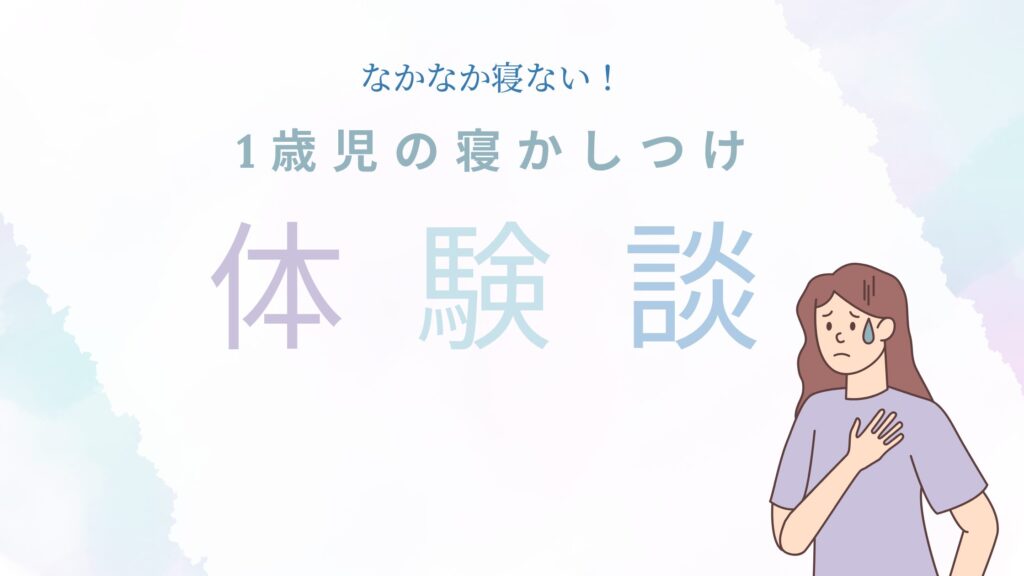
今では3人の子どもたちと毎晩一緒に寝ていますが、長男が1歳の頃は寝かしつけに苦労し、毎晩イライラしていました。
ここからは、私が体験した「1歳児の寝かしつけに悩んだ日々」をお話しします。
22時を過ぎても寝ない息子
長男が1歳の頃は、22時を過ぎてもなかなか寝てくれない日が続きました。
1歳児の睡眠時間は11〜14時間ほどが理想ですが、息子は22時に寝て朝6時に起きる生活。
睡眠時間を確保するため「遅くても20時には寝かせたい」と、毎晩19時頃には布団に入るようにしていました。
しかし、息子は布団の上で遊び続けて全く寝ません。
隣で寝たふりやトントンしても効果なし。
部屋を暗くしても、近くにあるおもちゃや絵本で1人遊びを始めてしまい、結局寝るのは毎晩22時を過ぎていました。
イライラして自己嫌悪
寝かしつけには毎晩2時間ほどかかり、その後に家事をしていました。
寝かせなければいけない焦りから「早く寝てよ」と心の中で何度も思い、次第にイライラが募っていきました。
怒ることではないと分かっていても、「もう寝るよ!」と強い口調で言ってしまうことも。
やがて「自分の育て方が良くないのかも」と悩み、自分の心に余裕がなくなっていきました。
些細なことで怒ってしまうことに自己嫌悪を抱くようになったのです。
親の焦りやイライラ、不安は子どもに伝わります。
子どもは寝ない、家事も終わらない、心身ともに疲れが溜まるという悪循環になっていました。
生活リズムを見直してみた
22時まで起きていた頃は、お昼寝が毎日2〜3時間ほど。
寝始める時間が遅いと18:00頃まで寝ていることもありました。
当時は「お昼寝してくれたら自分の時間ができる」と思っていたため、つい長く寝かせていたのです。
日中は児童館や公園に行くだけの生活で、体力が余っていたようでした。
そこで、お昼寝の時間を早め、夕方からのスケジュールを整えることにしました。
- 13:00〜15:00 お昼寝
- 17:00 お風呂
- 18:00 ご飯
- 19:00 就寝
早ければ16:00にお風呂へ入ることもあります。
お風呂を先に済ませると、自分も一緒に布団に入れるのでラクです。
お昼寝の時間を早め、お風呂とご飯を前倒しすることで、少しずつ就寝時間が早まりました。
生活リズムの改善は子どもの寝つきを助ける大きなポイントだと感じます。
寝室の環境を整えた
生活リズムと同じくらい、睡眠環境も大切です。
環境が整っていないと、なかなか寝つけなかったり、途中で起きたりします。
息子が1歳のころは寝室におもちゃや絵本があり、布団に入っても遊んでしまいました。
今は寝室におもちゃは置かず、「寝るための場所」と決めています。
また、ぐっすり眠れるよう寝具にも注目しました。
夏は暑さで寝苦しそうにしていたため、ガーゼケットを用意。柔らかくて肌触りがよく、通気性も良いため、安心して使うことができます。
冬は、軽くて温かい羽毛布団が重宝しています。
静かな環境と、眠りやすい寝具でリラックスできることが大切と実感しています。
まとめ:寝かしつけるのではなく、リラックスして一緒に寝よう

7年間の子育てを経て気がついた「最高の寝かしつけ」方法。
それはとてもシンプルで「子どもと一緒に寝ること」でした。
怒ったり、落ち込んだり、毎日悩んだ子どもとの夜の時間を少しだけラクにしてくれます。
子どもが1人で眠れるようになるのは、きっとあっという間です。人生100年のうち、親子で寄り添って眠れる時間はほんの数年しかありません。
「寝かせよう」と必死になるより、「一緒に寝ればいい」と思えたら、心に余裕が生まれ、子どもにも優しくできます。
親の心の余裕が子どもに安心感を与え、自然と眠りにつきやすくなるのです。
頑張りすぎない寝かしつけ、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
これからも「大切な人と、自分らしく生きる」ために情報発信していきますので、「年の差婚ナビ」を楽しんでいただけたらうれしいです!
最後まで読んでいただきありがとうございました!