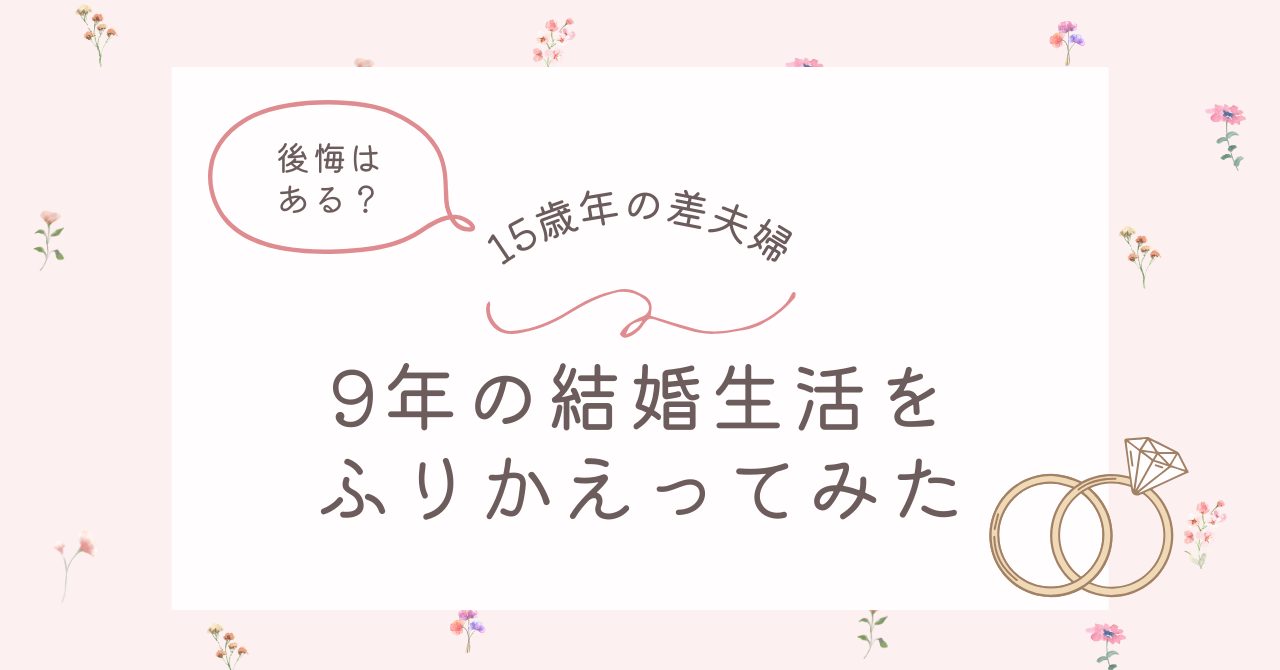お悩み女性
お悩み女性年の差がある彼と結婚したいけど、将来が少し不安…
10歳以上年の離れたパートナーと付き合っていると、「結婚して大丈夫かな」と不安になることもありますよね。
私自身、15歳年上のパートナーと結婚して9年になります。今では3人の子どもに囲まれてにぎやかな毎日を過ごしています。
付き合っているときには考えていなかった「家族になる」ということ。
仕事やお金の悩み、病気や介護などの老後の心配。
長い年月を一緒に歩むとき「年の差」という問題に不安を感じる方も多いですよね。
この記事では、年の差婚の不安や悩み、解決策を私の体験談をもとにお伝えします。
結婚に対する不安の原因を知ることで、将来をイメージしやすくパートナーと話し合うきっかけになるかもしれません。
「パートナーのことは大好き。でも、将来のことを考えると少し不安…」
そんな思いを抱えている方に、少しでも気持ちをラクにするヒントや安心を届けられたら嬉しいです。
\大切な人と、自分らしく生きる/
はじめまして!ちょびです。
15歳差婚を経験している私が、「なんとなく不安…」から「いつでも幸せになる」ために役立つ情報をお伝えしています。
プロフィールはこちら
パートナーとの年齢差が10歳以上なら「年の差婚」





「年の差婚」って何歳差なの?
「年の差婚」と呼ばれる年齢差に疑問をもつ方も多いのではないでしょうか。
実は、「年の差婚」に明確な定義はありません。
何歳差からが「年の差婚」と呼ばれるかは決まっていないのです。
そのため、一般的に10歳以上年の離れたパートナーとの結婚は「年の差婚」とされることが多いです。
私は15歳年上の夫と結婚して9年になります。
改めて「年の差婚」について、日々の生活を振り返りながら考えてみました。
年の差婚が不安になる5つの理由


パートナーのことは好きなのに結婚を考えると不安になる。
そんな気持ちになる方も多いのではないでしょうか。
特に、年の離れたパートナーと一緒にいる方は、将来に対して漠然とした不安を感じることがあります。
なぜ年の差があると「結婚」に不安を感じてしまうのでしょう。
年の差婚に対する不安の原因は以下の5つです。
- お金の不安
- 子どもに関する不安
- 老後の孤独
- 介護の備え
- 周囲の目や意見
これらの不安にどう向き合い、解決していけばよいのか、私の体験談を交えながら解説していきます。
お金の不安


人生の3大支出である「教育費」「住宅費」「老後資金」。
年の差婚では、同年代の夫婦とは異なるタイミングで支出や収入の変化が訪れます。
同年代であれば同じ期間に2人で収入を増やすことができますが、年の差があるとパートナーの定年退職が早くなり家庭の収入が減少するタイミングも早くなります。
- 「子どもが高校・大学に進学する時期に、パートナーがすでに定年退職している」
- 「60歳を超えても住宅ローンの返済が続いている」
思いのほか住宅費や教育費にお金がかかり、老後資金が貯められていなかったという問題もでてくるでしょう。
パートナーの年収が高ければ、1人の収入で将来への備えはできます。しかし、そうでない場合は2人で収入を増やすことが前提になります。
「専業主婦になりたい」「子育てに集中したい」と考えている場合には、パートナーと家計について早めに考えることが大切になります。



ちなみに、私は共働き夫婦です
2人とも健康なうちにしっかり働いて、教育費・住宅費・老後資金をバランスよく準備していきたいと考えています。将来への不安を解消するためにおすすめなのは、ライフプランを考えることです。
ライフプランとは、「どのように生きたいか」「何をしたいか」を考える人生の計画書です。
ライフプランを立てることで「いつ」「何に」「いくら」お金が必要になるのかが明確になり、将来への備えがしやすくなります。
詳しくは【3児FPママ実践】ライフプラン表を無料テンプレートで作成する方法(記事作成中)で解説しています。
子どもに関する不安


パートナーと年の差があると「子どもが授かれるのか」「子どもを育てていけるのか」と不安になりますよね。
「子どもは授かりもの」と言われますが、パートナーとの年齢が離れているほど、妊活や子育てにリミットがある現実にも向き合わなければなりません。
日本産婦人科医学会によると、男女ともに年齢を重ねるごとに妊娠率は低下するとされています。
| 女性の場合 | 男性の場合 |
|---|---|
| 32歳頃までは妊娠率が比較的安定 | 25歳未満と比べて、35歳以上では1年以内に妊娠に至る確率が半分になるというデータあり |
| 37歳以降は卵子の数・質が低下し、妊娠率が急降下 |
そのため、年の差が大きいほど、妊娠する確率が低くなる可能があります。
妊娠、出産を考えるのであれば、「いつまでに子どもを持ちたいか」「何人欲しいか」など、パートナーと話し合うことがとても大切です。



私たちは「子どもが欲しい」「兄弟の年の差はあけない」と決めたよ
私の場合はパートナーの年齢を考えると、早めに出産・育児に取り組んだ方が良いという結論に。
2人とも若いうちに乳幼児を育てられたので結果的に良いタイミングでした。
子どもの成長とともに親の体力は落ちますが、子どもの自立が進むと育児が少しラクになります。
自分たちに合った家族計画を立てることが、将来の不安を減らす第一歩です。2人で協力できれば年の差があっても子どもを育てることはできるでしょう。
老後の孤独


「2人の老後はどうなるのだろう——」
年の差婚では、パートナーの老いや先立たれる不安が、よりリアルに感じられるものです。
厚生労働省の発表によると、令和5年度(2023年)の平均寿命は以下の通りです。
| 男性 | 女性 |
|---|---|
| 81.09歳 | 87.14歳 |
日本の平均寿命は男性の方が6年ほど短く、年の差婚ではパートナーに先立たれる可能性は高くなります。若くして未亡人になる可能性もあるでしょう。
老後を見据えて一緒にいられる時間を考える必要がありますね。



私が45歳のとき、夫は60歳。私が60歳になるころには、夫は75歳
私が定年退職を迎えるころには、夫はもう後期高齢者。
2人で「のんびり老後を楽しむ」には少し遅いのかもしれません。
だからこそ、“いつか”を待たずに、いまを楽しむことが大切だと感じています。
パートナーと一緒にいられる時間はどのくらいあるのだろう。考えると少しさみしい気もしますが、いまを大切に想うきっかけになるかもしれません。
「いま」も「未来」もバランスよく楽しみたいですね。
老後の暮らしと、2人に残された時間について考えてみました。
詳しくは、【15歳年の差婚】パートナーと一緒にいられる時間は?大切にしたい思い出の配当とは(記事作成中)で解説しています。
介護への備え


年齢を重ねると、避けて通れないのが介護の問題です。
- パートナーの介護
- 義両親や自分の親の介護
将来的には、自分自身が介護される側になる可能性もあります。
内閣府のデータによると、65歳以上の要介護者は年々増加しています。特に75歳以上になるとその割合が急増することが報告されています。
参考:内閣府『高齢社会白書』
パートナーと年齢が離れていることで、自分がまだ元気なうちに介護ができる可能性は高いです。
「老老介護」になりにくいというのは、年の差婚のメリットといえるでしょう。
しかし、以下のような課題もあります。
- 仕事・介護・子育てを同時に担う可能性が高い
- 義両親の高齢化による介護



義母はすでに80代。私の祖母とあまり年齢が変わりません
つまり、育児・介護・仕事・家事が同時期に重なる可能性がとても高いのです。
そのために、いまからできることを始めましょう。すべてを1人で背負う必要はありません。
介護は“プロに頼る”という選択肢も立派な備えです。
介護について、私は以下のように考えています。
- 親の介護は介護サービスを活用
- 夫と自分の介護は子どもに負担をかけず、ヘルパーさんにお願いできるよう資金準備
- 介護は「完璧じゃなくていい」と割り切る
年の差婚では、同年代よりも早く介護のタイミングが訪れるでしょう。
育児も介護も「1人でがんばらない」「頼れるものには頼る」を意識して気持ちをラクに、自分を大切にして生きたいです。
周囲の目や意見


「そんなに年が離れていて大丈夫?」
年の差婚をしていると、周囲から心配されることはありませんか。実際、私も夫と付き合う前に友人からこう言われたことがあります。
「えっ、15歳上? 私だったらちょっと考えるかな…」
否定的というよりは、「現実的に考えることがたくさんあるよね」という意見でした。友人は、結婚や老後のことまで見据えていたのだと思います。
否定的な意見にはモヤモヤすることがあるかもしれません。しかし、そうした言葉がきっかけで、真剣に将来を考えるようになるのも事実。自分にとって大切なことを見つめ直す機会になるでしょう。
私の場合、家族からの強い反対はありませんでした。
でも、母はきっと心のどこかで心配していたと思います。



それでも私の気持ちを優先し、応援してくれたことに感謝です
年の差はあくまで生まれた年が違うだけ。年齢という数字が違うだけです。
周囲の目や意見はまったく気にする必要がありません。
それよりも大切なのは「お互いを尊重する」ということ。
そして、自分の人生を楽しめているかどうか。それがすべてだと思っています。
【体験談】結婚生活9年をふりかえる


15歳年上の夫と結婚して9年。ふりかえってみると、いろいろなことがありました。
- 結婚して1年後に第一子が誕生
- 生後6ヶ月の子どもと共に、夫の実家で同居生活がスタート
- 第二子、第三子が誕生
- 末っ子が2歳になったタイミングで仕事に復帰
現在は私たち夫婦と子ども3人、そして義母+ねこの3世代完全同居です。
🏠️同居エピソードについては別の記事で紹介していきますので、興味があればそちらもぜひ。
あっという間に未子も3歳になり、結婚から9年が過ぎました。時が経つのは早いなと感じつつも、夫との関係はあまり変わらない気がします。
お互いに干渉しない性格だからか、喧嘩もほとんどありません。疲れやストレスが貯まると相手に冷たい態度をとってしまうこともありますが、時間が経てば自然と元通りになります。
これからも尊敬と感謝の気持ちを忘れず、お互いの時間を大切に過ごしていきたいです。
年の差婚、後悔してる?の答え
正直に言うと、年の差婚そのものは後悔していません。
年の差は関係なく「夫と結婚したことは後悔していない」というのが正しいかもしれません。
ですが、本当は4人目を望んでいた私。子どもに関しては「もっと準備ができていれば…」という後悔があります。
- 「もっと早く資産形成に取り組んでいれば…」
- 「ライフプランをしっかり立てていたら、選択肢は増えたかもしれない」
いまでも過去に戻りたいと思うことがあります。でも、過去を悔やんでも未来は変えられません。
「3人の子どもたちに選択肢の自由を与えたい」「夫との時間をもっと楽しみたい」という新たな目標を持って、前を向いて歩いています。
そして、「お金がないから結婚や子どもを諦める」という選択から「お金と向き合って結婚や子どもを望める」という選択をする人がひとりでも増えるように情報を発信していきます。
まとめ:年の差婚は不安ばかりじゃない。2人で明るい未来を


年上のパートナーとの結婚を迷う気持ちはよくわかります。
「お金」「子ども」「老後」「介護」など、結婚すると環境は大きく変わります。
ですが、これらの悩みは年の差婚に限ったものではありません。
- 生活していくにはお金が必要
- 子どもを望むかどうか
- 年老いたときの病気や介護
生きていれば誰にとっても大きな問題となるでしょう。
大切なのは「年齢差」ではなく、パートナーとどんな人生を歩みたいかということ。
誰かの価値観ではなく、自分で選んだ人生を後悔のないように生きることです。
自分らしく、心から納得できる人生を歩めますように。
これからも「大切な人と、自分らしく生きる」ために情報発信していきますので、「年の差婚ナビ」を楽しんでいただけたらうれしいです!
最後まで読んでいただきありがとうございました!